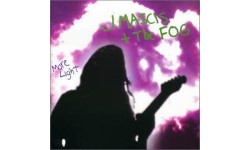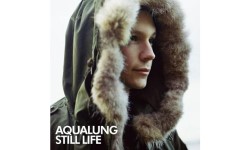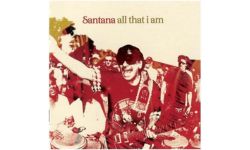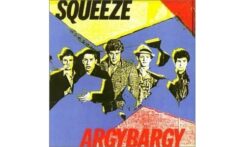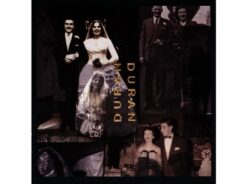①クラシックとロックを融合させた…
1967年にイングランドで結成されたProcol Harum(プロコル・ハルム)。クラシックとロックを融合させた“プログレの開拓者”として、今でも高く評価されています。
代表曲「A Whiter Shade of Pale(青い影)」は、まだデビュー前の1967年にリリースされた曲で、全米5位を記録。
イギリスではビートルズ「All You Need Is Love(愛こそはすべて)」に首位を譲るまで6週連続1位に居座り続け、世界中で1000万枚以上を売り上げた大ヒットシングルです。
荘厳で深みのあるオルガンのイントロが静かに心をつかみ、そこに重なるのはゲイリー・ブルッカーの少し寂しげで味わい深い歌声。気づく間もなく、その世界観に引き込まれていきます。
半世紀以上前に生まれた曲とは思えないほど色あせずに、今も世界中で愛され続けている――まさに時を超えた名曲です。
【PROCOL HARUM - A Whiter Shade Of Pale - promo film #1 (Official Video)】
②歌詞と和訳
Songwriter(s) - Gary Brooker, Keith Reid, Matthew Fisher
We skipped the light fandangoTurned cartwheels 'cross the floorI was feeling kinda seasickBut the crowd called out for moreThe room was humming harderAs the ceiling flew awayWhen we called out for another drinkThe waiter brought a tray
And so it was that laterAs the miller told his taleThat her face, at first just ghostly,Turned a whiter shade of pale
She said, “There is no reasonAnd the truth is plain to see.”But I wandered through my playing cardsWould not let her beOne of sixteen vestal virginsWho were leaving for the coastAnd although my eyes were openThey might have just as well’ve been closed
And so it was that laterAs the miller told his taleThat her face, at first just ghostly,Turned a whiter shade of pale
サビに出てくる「粉屋」。覚醒剤のことを指しているんじゃないかという説もありますが、作詞のキース・リード本人がそれを否定。むしろ有力なのは、14世紀の物語集『カンタベリー物語』に登場する“粉屋の亭主が若者に妻を寝取られる話”からの発想という説。でもこれも、直接の引用ではないそうです。
じゃあ粉屋って、結局なんなんでしょうね?比喩なのか、それとも本当に粉屋なのか――これはもう謎のままです。
でも、このわかりにくさもこの曲の面白いところ。はっきりしないからこそ想像がふくらんで、気づく間もなくどんどん曲の世界観にハマっていくんですよね。
③デビューアルバムさえまだ…
荘厳で叙情的な雰囲気をまとったプロコル・ハルムのデビューシングル「青い影」。その響きが世界に広がるのに、時間はほとんどかかりませんでした。デビューアルバムさえまだ出していない段階で、バンドは一気に“時の人”となったのです。
発売から50年以上たった今も、この曲はミュージシャンを含めた世界中のファンに愛され続けています。けれど、その歩みが最初から順調だったわけではありません。
「青い影」がシングルチャートで1位をキープしていたさなかに起きたのは、契約トラブル。ギター、ドラム、そしてマネージャーまでもが解雇されるという状況に追い打ちをかけたのは、トラブルのせいで「青い影」のシングル版とこれから出す予定だったデビューアルバムの発売権を持つレーベルが違ってしまったこと。
結果、母国イギリスでのデビューアルバムには、「青い影」が収録されないという異例の事態に。
そしてもうひとつ、首をかしげたくなる出来事も。最初に制作されたPVには、曲とのつながりがわかりにくいベトナム戦争の映像が使われていたのです。撮り直しに至るのも、当然といえば当然でした。
その後のプロコル・ハルムのイメージを決定づけた「青い影」。しかし、名曲を生み出したがゆえに背負うことになったのは、それを超えるものを求めるファンの大きな期待と、重いプレッシャーでした。華やかな成功の裏にはそんな影が潜んでいたんですね…。
④G線上のアリアを思わせる…
「青い影」は、バッハのカンタータ第140番「目覚めよと呼ぶ声あり」に影響を受けて作られたと言われています。
でも、曲の空気を決めているのは、やっぱりあの「G線上のアリア」を思わせるオルガンの旋律。そこからの影響を強く感じる人も多いはず。
発表当時、この曲をあのジョン・レノンが「この曲以外は聴く価値がない」「人生でベスト3に入る曲」と語ったという逸話も残っています。
その評価を裏付けるように、2009年にBBCが発表した「過去75年間、イギリスで最もラジオで流れた曲」では、リスナーが一番多いRadio 2部門で1位。2位はクイーンの「Bohemian Rhapsody」、5位はブライアン・アダムスの「(Everything I Do) I Do It For You」。
この顔ぶれの中にあっても、「青い影」の存在感はやはり群を抜いています。
数多くのカバーが作られていることも、この曲が時代を超えて愛されている証しですね。中でも、サラ・ブライトマン、マイケル・ボルトン、アニー・レノックスによるバージョンは、それぞれの持ち味が光る名演。CDで手に入れやすく、聴き比べても面白いですよ。
「青い影」は1988年、日産シルビアS13型のCMで流れていたので、なんとなく耳にしたことがある…という人も多いかもしれません。あの映像とともに聴いたメロディが、今でも頭に残っているという方もいるでしょう。松任谷由実さんも“創作の原点”として何度も名前を挙げていますし、本当に心に強く残る曲だなと感じます。